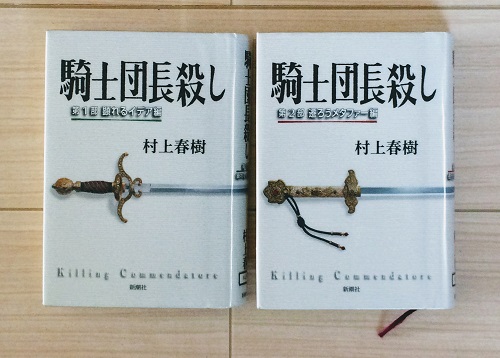
村上春樹『騎士団長殺し』を読んだ。上下巻で1000ページ超えの長編。とてもおもしろかった。読む前に想像していたのよりずっと、意外なほどおもしろかった。
村上春樹の小説を読むのはたぶん『海辺のカフカ』以来。数えてみたら18年ぶり(そんなに経つの!?)。かつて好きでよく読んでいたけれども、特に理由もなく遠ざかってそのままになっていた。
『騎士団長殺し』の発表は2017年。先日ふと図書館で見かけたので借りてきた。読み始めたらすごくおもしろい。物語にぐいぐい引き込まれる。毎日少しずつ細切れに読んでいたのだけど、本を手に取るたびに物語世界にどっぷり没入できることが幸せだった。ページの上に繰り広げられる世界と、私が生きてる現実の日常を行き来できる醍醐味。
話をものすごく大雑把にいうと、妻に離婚を切り出されて喪失感を味わっている男(画家)が、謎めいた隣人やいわくつきの絵画作品や騎士団長を名乗る超常的存在と接するうちに、非日常の世界につながる通路への入口を見つけ、そこから生還、そして喪失が再生される、というもの。
理屈では説明できない・筋がとおらない状況やエピソードがたくさん出てくるのだけど、読んでいる側としてはそれが不満だとか意味不明だということは感じなかった。精神的な世界ではこういうことも起こるだろうし、こういう見方や考え方もありえるのだろうなーと自分なりに納得しつつ読んだ。
そういうふうに読めるようになったのは、私自身の成長というか変化なのかも。これまでに読んだ村上春樹作品には、「おもしろいけど解釈が難しい」とか「結局どういうことだったのか辻褄がよくわからない」という印象が少なからずあった。でも今は、現実味や整合性の答え合わせをするために小説を読んでるわけじゃないもんな、というおおらかさ(?)を持てるようになったというか。書いてあることを読むというより、読みながら自分が何を感じたのか、何を考えたのかに気づくことのほうがおもしろいと思うようになったというか。
主人公がある入口から非現実空間に入り込み、そこで人ならぬものに出会って自分の意識が変わる・自分を取り戻すという構成に、不思議の国のアリスとか、映画「ラビリンス」とか、小説では梨木香歩の『f植物園の巣穴』とか十二国記を連想した。どれも好き。私はこういう系統が好みなのかと再発見。探せばまだまだありそうだな。
あと、ここまでの感想とはちょっと別枠ながら、レビュー等でさんざん言われてるとおり性的な行いや描写が多すぎ。それも含めて村上春樹的といえばそうかもしれないし、もちろん作品にとって必要だから書いてるんだろうけど、いやいや、そこまで本当に必要かね?と言いたくなる。さらに、中学生女子が自身の胸のサイズについての悩みを中年男性に相談するシーン(しかも何度も)、そんなのぜったい現実的じゃないから!これだけは、さっき「小説に必ずしも現実味を求めない」と言ったのとは別軸。そのシーンが出てくるたびに「マジでもういい加減にして」と言いたくなったわ。
ともあれ、楽しく有意義な読書の時間だった。娯楽小説!というわけでもなく、爽快さや痛快さとも違うのに、創作の力で1000ページを読ませて何かしら心に影響や引っ掛かりを残させる村上春樹、やっぱりすごいなというか、読み飛ばしてる作品も読んでおこうという気になった。

